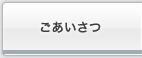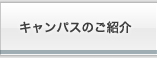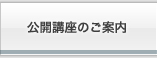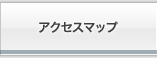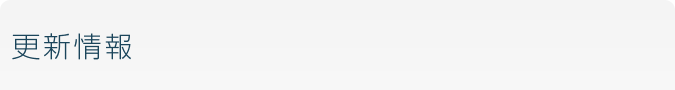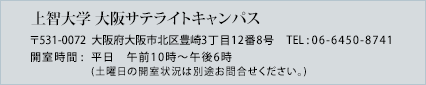上智大学110周年記念行事 ユニセフセミナー実施報告
2023年10月9日(祝)、上智大学大阪サテライトキャンパスと兵庫県ユニセフ協会は、若年世代に教育活動を通した国際協力と支援の在り方について理解を深めてもらうことを目的とした共同プログラム、【“教育”から考える国際協力と支援の道~若者たちとこれからの国際教育~】を上智大学大阪サテライトキャンパスにて開催しました。中学生高校生や教育機関に所属される方々をはじめ、さまざまな参加者が、国内外で活躍されている方々の講演や活動報告を通し、「教育」面から国際協力と支援への理解を深める機会となりました。
プログラムの概要はこちらをご覧ください。

冒頭、永井敦子上智大学学生総務担当副学長から本学における国際協力・支援に繋がる教育プログラムや大学全体の取組についての紹介がありました。特に、上智大学とユニセフとの関わりにおいて故緒方貞子名誉教授を抜きにしては語ることができないことに言及。今回のタイトルにもある「国際協力」とは非常に包括的な概念であり、国際協力への多面性を理解し自分の役割を見出すことが、国際協力への第一歩といえるなかで、本学はユニセフをはじめ国連や国際機関と綿密に連携し、国際機関や国際協力の分野で活躍する数多くの優れた人材を輩出してきたことを紹介。現在もそのような伝統を受け継ぎ、先達に続く人材を今後も持続的に送り出してゆくために、一人ひとりの学生の皆さんを支援したいと語りました。
アフリカのスラムに学校を作る~子どもたちの笑顔、命の輝き~

ケニアのスラム街・キベラで貧困の子どもたちの学校「マゴソスクール」を運営する早川千晶氏を招いて講演が行われました。早川氏は大学で外国語を習得し、在学中に飛行機を使わず自身の足で旅をすることを始めたと語りました。旅先でさまざまな人々と触れ合う中で、自身の胸の内に芽生えた世界への疑問に向き合いました。アジア、中東、ヨーロッパを経てアフリカを東から西に陸路で旅をした時に、アフリカがいかに困難な社会的事情がある地域であるかを知り、日本に帰らずケニアで働きながら生きていくことを決意。そこから今の活動に至るまでの経緯や様々な出来事、当時の想いを紹介しました。

早川氏が住むケニアの首都ナイロビは、人口約500万人の大都市ですが、車で10分離れた場所にはキベラスラムがあり、人口の約半数がスラムに住むと言われるほど貧富の差が大きな場所であることを、航空写真やスラム街で生きる人々の生活風景を撮影した写真を介して紹介。「スラムの暮らしはケニア人ですら知らない。隣りあわせでも知ろうとしなければ知れない。」と現地のリアルな姿を語りました。
早川氏は、キベラスラムで生まれ育った親友の活動を支えはじめたことが、今のマゴソスクールを運営する原点だと語りました。黒板とチョークしかない寺子屋で、歌や学びを与えた親友を支えることから始まったマゴソスクールは、さまざまな困難を抱えながらも生きることを諦めない人々が集まり、病と貧困と闘い、常に死と隣り合わせにある生活環境の過酷さがあるなかでも、希望がある場所だと語りました。
絶望から立ち上がり希望を持って卒業したマゴソスクールのOBOGが、大学で学んだ新しい知識や経験を持ち帰り革新的な活動を展開しているエピソードなどを紹介。マゴソスクールにソーラーパネルを設置し、コンピューターのプログラマー養成学校を作る卒業生もいれば、キベラスラム若者代表として世界会議や国連会議に出席し活躍する卒業生がいると語ります。「近年では日本の若者がマゴソスクールを訪ねて若者同士で意見交換し合う機会もあることを非常に嬉しく思う」と、日本とケニアの若者たちの交流する様子を紹介し参加者の関心を集めました。参加者からは「今のアフリカの様子を知る事ができ、自分ができることを考えるきっかけとなった。」などの声を頂きました。
六甲学院中学・高等学校 社会奉仕活動報告

六甲学院中学・高等学校社会奉仕委員会の委員長(高校3年生)と副委員長(高校1年生)が、日々の活動や社会奉仕委員を通して感じていることについて報告しました。
まず、地域活動の例としてゴミ出しボランティアを紹介しました。ゴミ出しが困難な地域の方に代わってゴミを出す活動は、相手の顔が見えるボランティア活動であるため、言葉のやりとりを通して嬉しい気持ちになることも多いと、活動の写真を投影しながら紹介しました。ゴミ出し活動に参加している副委員長は、「地域の人と関わることで地域の輪が広がることにも気が付ける活動でもあり、今後も誇りを持って続けたい。」と語りました。
続いて委員長が、インド募金は校内で行われている募金活動であり、その歴史は1977年に遡ることを紹介。任意参加の募金活動であるが、1人あたり200円を目標として設定している。200円は食堂で売っているパンの価格に相当しており、パンの購入を1回我慢することで活動に参加して欲しいという思いがある。集まった募金はインド北東部にあるジャールカンド州のダンバードにあるダミアン社会福祉センターに送金され、センターの中の「デブリット・ハウス」と呼ばれる施設で、ハンセン病患者を親に持つ子どもの学費や給食費にあててもらっている。インド募金は募金を送るだけの活動ではなく、生徒が実際にインドを訪問し、募金がどういう人たちのためにどのように役に立っているかを学習し、支援している子供たちと直接出会って交流することも目的としている。インドを訪問した生徒は帰国後、文化祭やホームルームを通して全校生徒に体験を共有する機会を設けていることを説明。「インド募金の意義は社会的弱者という方に思いを馳せるきっかけとなる活動である。月に1度の募金を通して彼らに思いを馳せ、知る機会に繋げることに社会奉仕委員の活動の意味があると考える。より深く社会問題を知り、自分の考えを持つことが行動に移すきっかけになると考えている。このことは六甲学院の教育精神でもある“他者のために、他者とともに”の原点であると思うと共に、社会奉仕委員の活動を通して、現代の社会問題を全校生が考える機会をつくることに意義があると考える。」と委員長は語りました。参加者からは「活動を通じ援助を受ける人々の内発的な発展の必要性に気付き、将来の目標に繋がった二人のお話は素晴らしかったです。」などの感想が寄せられました。
東ティモールの教育研究から考える国際支援

須藤氏は六甲学院を卒業後、本学総合人間科学部教育学科に進学し教育学を学ばれました。現在は東京大学大学院教育学研究科学校教育高度化専攻博士課程に在籍され、東ティモールの教育、特に教授言語問題を研究されています。講演の冒頭で須藤氏は、六甲学院高等学校在学中にインドを訪問し、貧困を目の当たりにしたことが途上国の教育研究者を目指した契機だったと語りました。
研究のフィールドワークとしている東ティモールは、国民の約64%が30歳以下という若い国であり、96%の人々がカトリックを信仰する東南アジアの国であることを紹介。特に複雑な歴史的背景の影響を受け、公用語と実用語のほか、地域言語が20以上も存在する多言語国家であり、国民の年代によって話せる言語が異なるため、教育現場では教師と生徒の間で言語統一が無い教授言語問題を抱えているという現状を語りました。
須藤氏は現在、途上国、主に東ティモールにおける教育と言語多様性、へき地における教授言語問題の研究を行っていることを研究集計データやフィールドワークで訪れた先々での写真を交えながら紹介。研究を通して東ティモールが援助に頼らざるを得ない途上国の現状や、小規模国家であるからこそ抱えているジレンマを研究活動を通して感じる機会もあると語ります。教育はしばしば「べき論」に傾きがちであるが、実際に現地の人々は外からの支援をどのように感じているのか、フィールドを冷静に見つめる必要があるのではないかと研究者ならではの疑問を投げかけます。
また、自身が携わっている教授言語問題は途上国特有の問題ではなく、単一言語国家と思われがちな日本にも存在すると指摘します。これらからの国際支援を考える際には、支援してあげるではなく、知見を出し合う・学びあう、ともに立つという姿勢が大事だと強調しました。
自分のやっている研究は今困っている子どもたちの何かを即時的に解決できるものではない。しかし東ティモールに携わる研究者が少ないからこそ、研究を介し積極的に研究者同士が関わりチームを組むなどして研究が発展していくことで、次世代の教育者や教育の担い手を支援していくという役割があるのではと思っている。研究は机上の空論になりがちだが、理論と実践の懸け橋になれるような研究者を目指してゆきたいと今後の抱負を語りました。参加者からは「国際協力と言うテーマのとき、自分は相手ばかりを考えていたが、まずは自分の足元を見るのが大事だと気づいた。」といった感想が寄せられました。